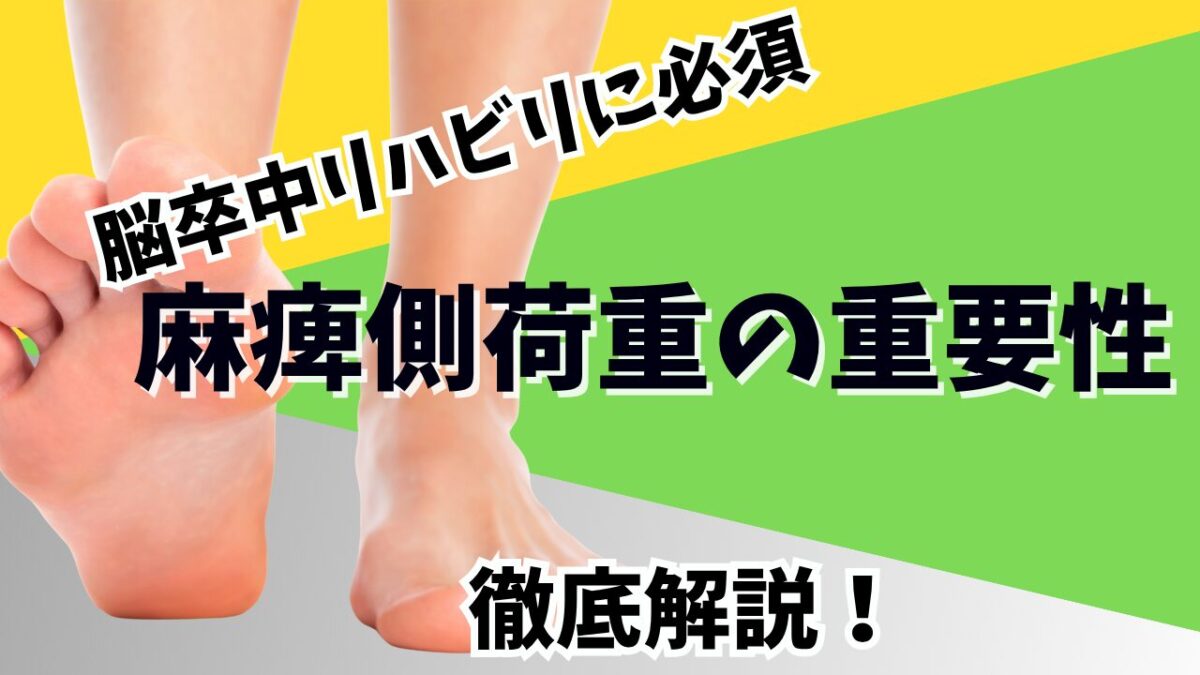脳梗塞リハビリActive豊橋の戀田です!
きっと多くの方が直面する悩みの一つについて解説していきます!
脳卒中のリハビリを受けている方やご家族の多くが、リハビリ場面で一度は耳にする言葉があります。
それは「麻痺側に体重をかけましょう」という指導です。
しかし実際の患者さんからは、こんな声が聞かれます。
「麻痺側に乗ろうとすると膝がガクッと折れそうで怖い」
「グラつく感じがして、結局健側に頼ってしまう」
「頭では分かっているのに、体が怖がってしまってできない」
リハビリの現場でこうした悩みはとても一般的です。
では、なぜそれでも私たち理学療法士は「麻痺側に荷重が乗る」ことを重視するのでしょうか?
今回はその理由と、実際の練習方法について、脳卒中認定理学療法士の視点とエビデンスを交えてお話しします。
1. なぜ麻痺側に体重をかける必要があるのか?
学習性不使用の悪循環
脳卒中では、片側に麻痺が残ることでバランスの崩れが生じます。
人は無意識に安全なほう(健側)に体重をかけてしまうため、麻痺側にはほとんど荷重されなくなります。
こうして起こるのが、いわゆる「学習性不使用(learned nonuse)」です。
麻痺側を使わない状態が続くと、その脚はさらに筋力やバランス機能が落ち、ますます荷重が難しくなり、健側に頼る悪循環が進んでしまいます。
この負のスパイラルを断ち切るには、意図的に麻痺側へ体重をかける練習を取り入れることが不可欠です。
CBWSによる環境調整の効果
リハビリでは単に「頑張って麻痺側に乗りましょう」と声をかけるだけでは足りません。
実際には、環境を工夫して麻痺側に荷重せざるを得ない状況を作ることが有効とされています。
その代表例がCBWS(Compelled Body-Weight Shift)という方法です。
具体的には、健側の靴に数ミリのリフトを入れ、わずかに高くして麻痺側に重心が移動しやすいように調整します。
- Mohapatraら(2012)は、急性期脳卒中患者11名を対象に、標準リハにCBWSを2週間追加した結果、通常リハ群よりも麻痺側荷重が増え、歩行速度も改善したと報告しました。
- Aruinら(2012)は、慢性期の患者を対象に6週間のCBWSを行い、麻痺側荷重比が約10%増加、歩行速度も向上し、さらに3か月後も効果が維持されたと述べています。
👉 このように、環境を変えるだけでも麻痺側の使用が促されることが示されており、「麻痺側に体重をかける」という行為が回復の鍵を握っていることがわかります。
2. 歩行・バランス改善との関係
麻痺側に体重をかけることは、ただ立ちやすくするためだけではありません。
実は、歩行の支持期や体重移動の質を改善するための重要な要素です。
- Ravichandranら(2022)による系統レビューでは、荷重支持を重視した歩行特異的訓練が、歩行対称性や歩幅、歩行速度の改善に有効であることが報告されています。
- Shresthaら(2022)は、多方向ステップ+荷重移動訓練を4週間追加した群が、BBS(Berg Balance Scale)とFGA(Functional Gait Assessment)で有意な改善を示したと述べています。
- さらにLyuら(2023)のネットワークメタ解析では、体重支持式トレッドミル(BWSTT)が動的バランス改善に有効であることが示されました。
👉 これらの研究から、麻痺側荷重は立位のみならず、歩行やバランスの機能改善にも直結することがわかります。
🟢 BBS(Berg Balance Scale:バーグバランススケール)
BBSは「バランス能力」を30点満点で測る国際的に使われている評価法です。
脳卒中リハビリだけでなく、高齢者の転倒リスク評価にも活用されています。
評価内容:
14項目のバランス課題(例:立ち上がり・立位保持・目を閉じて立つ・前屈・方向転換など)を行い、それぞれ0〜4点で採点します。
特徴:
座位から立位、動的な体重移動まで含むため、日常生活に近いバランス能力を把握できます。
転倒リスクの目安:
多くの研究で 45点未満は転倒リスクが高いとされています(Berg et al., 1992)。
脳卒中リハとの関連:
BBSの点数が改善すると、歩行の安定性・自立度も向上する傾向が報告されています。
👉 つまりBBSは、バランス機能の客観的な変化を追える信頼度の高い指標です。
⸻
🟢 FGA(Functional Gait Assessment:機能的歩行評価)
FGAは「歩行時のバランスや機能性」を10項目で評価するツールです。
歩くだけでなく、方向転換・段差昇降・目を閉じて歩く・速さの変化など、実生活に近い動きを含むのが特徴です。
評価内容:
10項目(例:平地歩行・方向転換・障害物をまたぐ・目を閉じて歩く・階段昇降など)を各0〜3点で評価、満点は30点です。
利点:
歩行スピードだけでは分からない「環境変化に対応する力」や「転倒しやすいシーンでの安定性」がわかる。
脳卒中リハとの関連:
Shresthaら(2022)は、荷重移動+多方向ステップ練習を追加した群でFGAが有意に改善したと報告しており、実践的歩行能力の回復指標として有効です。
👉 FGAは、歩行の質やバランスの課題を見つけるための“実用的な歩行評価”として重宝されています。
⸻
🟢 BWSTT(Body Weight Supported Treadmill Training:体重支持式トレッドミル歩行訓練)
BWSTTはハーネスなどで体重を一部免荷しながらトレッドミル上で歩行訓練を行う方法です。
体重の一部を機械が支えるため、麻痺側脚にも安全に荷重をかけながら歩行パターンを練習できるのが特徴です。
メリット:
- 初期段階から麻痺側への荷重を促しやすい
- 歩行パターンの反復回数を増やせる(集中練習)
- 体重を支えているため転倒リスクが低く、恐怖心を軽減
エビデンス:
Lyuら(2023)のネットワークメタ解析では、BWSTTが脳卒中後の動的バランス改善に有効と報告されています。
また早期からの歩行再学習をサポートする介入としても推奨されています。
臨床活用例: 安全にステップ反復練習ができるため、特に急性期〜回復期の患者さんに適しており、麻痺側の支持期強化にもつながります。
👉 BWSTTは、麻痺側に荷重を促しつつ効率的に歩行練習ができる近年注目のトレーニング方法です。
3. 練習の実際:止まった状態から動いた状態に!
基本的な静止状態での練習
- 鏡を使った荷重確認(Aruin et al., 2012) 鏡の前で立ち、左右の荷重が均等かを目で確認しながら調整します。
- CBWSによる荷重誘導(Mohapatra et al., 2012) 健側の靴に3〜5mm程度のリフトを入れ、自然に麻痺側に荷重がかかるようにします。
- 支持具を徐々に減らす練習 初めは手すりやパラレルバーで安定を確保し、徐々に手を離して荷重を麻痺側に委ねていきます。
動的な荷重練習
- 前後・左右・斜めへの体重移動(Shrestha et al., 2022) 足幅を調整しながら、麻痺側への重心移動を少しずつ深く、長く保てるようにします。
- 多方向ステップ練習(Shrestha et al., 2022) 一歩を前・横・後ろへ出しながら荷重を移すことで、実生活に近い動作を再現します。
- トレッドミル+荷重フィードバック(Lyu et al., 2023) 圧センサー付きトレッドミルなどを活用し、歩行中の麻痺側支持期を強化します。
- 方向転換や段差昇降練習 曲がる、下がる、段差を上がるなど、多彩な動作を取り入れて麻痺側荷重を実生活に応用します。
安全のために、膝の過伸展(反張膝)や膝折れに予防に装具(AFOなど)を適宜併用し、転倒リスクを最小化しましょう。
4. フィードバックの活用で上達を加速
荷重訓練の効果を高めるポイントは、「自分がどれだけ麻痺側に乗れているか」を知覚できることです。
- 視覚フィードバック:鏡やモニターで荷重比を見える化(Ravichandran et al., 2022)
- 聴覚フィードバック:センサーで荷重到達時に音を鳴らす
- 触覚フィードバック:セラピストのハンドリングで体幹や股関節を誘導
👉 複数の感覚を使って体重移動を“体で覚える”ことで、より短期間で安定した荷重コントロールが獲得できます。
5. 麻痺側荷重が開く未来
ここで忘れてはいけないのは――
「麻痺側に体重をかけられるようになること」自体はゴールではないという点です。
麻痺側への荷重が増えることで得られるのは、次のような変化です。
- 歩行の支持期が安定し、転倒リスクが減る
- 健側への過度な負担が減り、関節痛や疲労を防げる
- 体重移動がスムーズになり、段差昇降や方向転換が楽になる
- 何より、「また自分の脚で歩ける」という自信が戻ってくる
理学療法士として現場に立つ中で、麻痺側にきちんと体重をかけられるようになった瞬間に患者さんの表情がぱっと明るく変わる場面を何度も見てきました。
その瞬間こそが、再び自由に歩ける未来への扉が開いた証拠です。
荷重促通は単なるリハビリの一手法ではなく、自立と安心を取り戻すための第一歩なのです。
まとめ
麻痺側に体重をかけることは、単なる筋トレではありません。
非麻痺側への依存を減らし、歩行とバランスを取り戻す鍵となる介入戦略です。
エビデンスはこう示しています:
- CBWSは荷重対称性と歩行速度を改善(Mohapatra et al., 2012; Aruin et al., 2012)
- 荷重特異的訓練は歩行対称性やバランス機能を向上(Ravichandran et al., 2022; Shrestha et al., 2022)
- BWSTTなどの技術は動的バランス改善に有効(Lyu et al., 2023)
そして私たちの臨床経験が示すのは、麻痺側に“乗れる”ようになることで患者さんの心が変わるということ。
不安から解放され、もう一度自分の足で歩けるという希望を感じられるようになります。
もし今、「麻痺側にうまく体重をかけられない」「立つのが怖い」と悩んでいるなら、焦らず、でもあきらめずに一歩ずつ麻痺側へ荷重を促す練習を続けましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
参考文献
Aruin, A. S., Rao, N., Sharma, A., & Chaudhuri, G. (2012). Compelled body-weight shift approach in rehabilitation of individuals with chronic stroke. Topics in Stroke Rehabilitation, 19(6), 556–563.
Mohapatra, S., Aruin, A. S., et al. (2012). Compelled weight-bearing shift in individuals with acute stroke: A comparative study. Journal of Rehabilitation Research & Development, 49(2), 289–296.
Ravichandran, R., et al. (2022). Effect of gait-specific weight-bearing interventions on physical performance among subjects with stroke: A systematic review and meta-analysis. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 19, 83.
Shrestha, R., Kim, M., & Park, J. (2022). Effects of multi-directional step exercise with weight shifting on balance and gait in stroke patients: A randomized controlled trial. Scientific Reports, 12, 17529.
Lyu, T., Wu, D., Zhang, Q., et al. (2023). Comparative efficacy of gait training for balance outcomes after stroke: A network meta-analysis. Frontiers in Neurology, 14, 1093779.