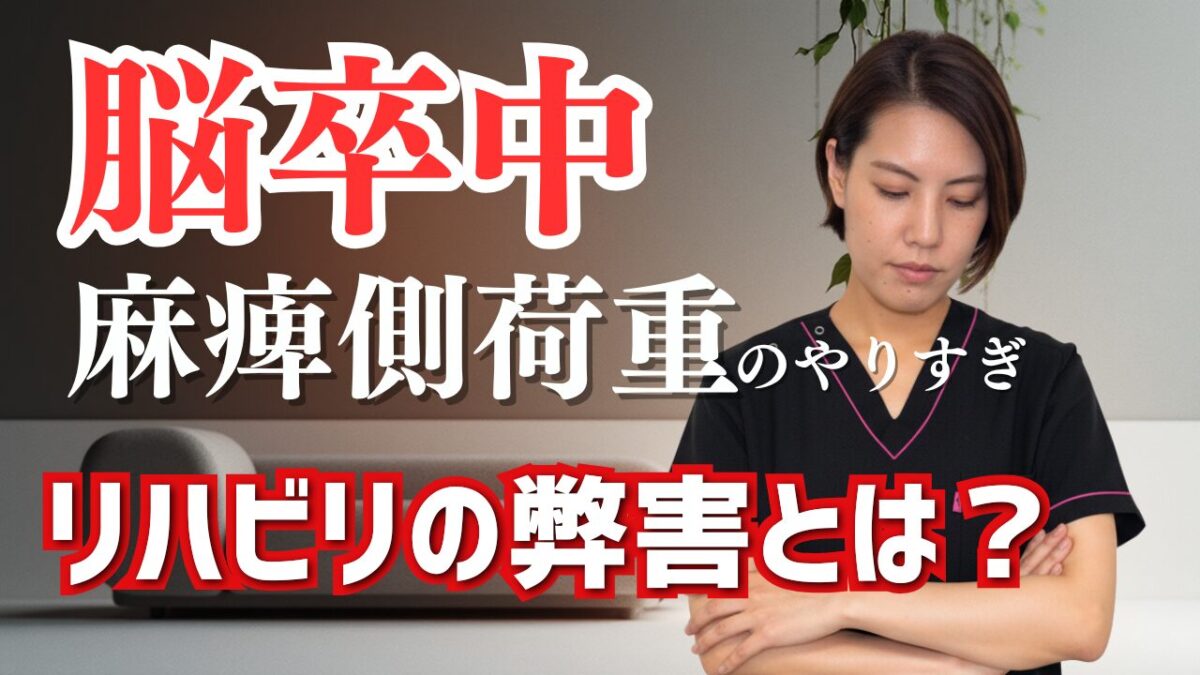脳梗塞リハビリスタジオActive豊橋の河合です。
リハビリの現場で、「麻痺側にもっと体重をかけてください!」という声は日常的に聞かれますよね。麻痺側への荷重は、回復を促す上で非常に重要な要素です。しかし、実はこの「麻痺側荷重」、
ただ強く促せば良いというものではない、ということをご存知でしょうか?
今日は、麻痺側荷重を「やりすぎ」た場合にどんな弊害が起こりうるのか、そして、どうすれば安全かつ効果的に麻痺側荷重を促せるのかについて、最新の知見も交えながら分かりやすくお伝えします。理学療法士の先生方や関連職種の皆様にとって、日々の臨床のヒントになれば幸いです。
麻痺側荷重を「促しすぎる」とこんな問題が…
麻痺側への荷重は大切ですが、患者様の身体がまだ準備できていない段階で無理に促すと、様々なリスクが生じます。
1. 関節や軟部組織への過度なストレス
麻痺側の筋力や関節の安定性が不十分な状態で無理に体重をかけさせると、関節に不自然な「ズレる力(剪断力)」がかかり、痛みや関節の変形、軟部組織の損傷リスクが高まります(Giarmatzisら, 2025)。
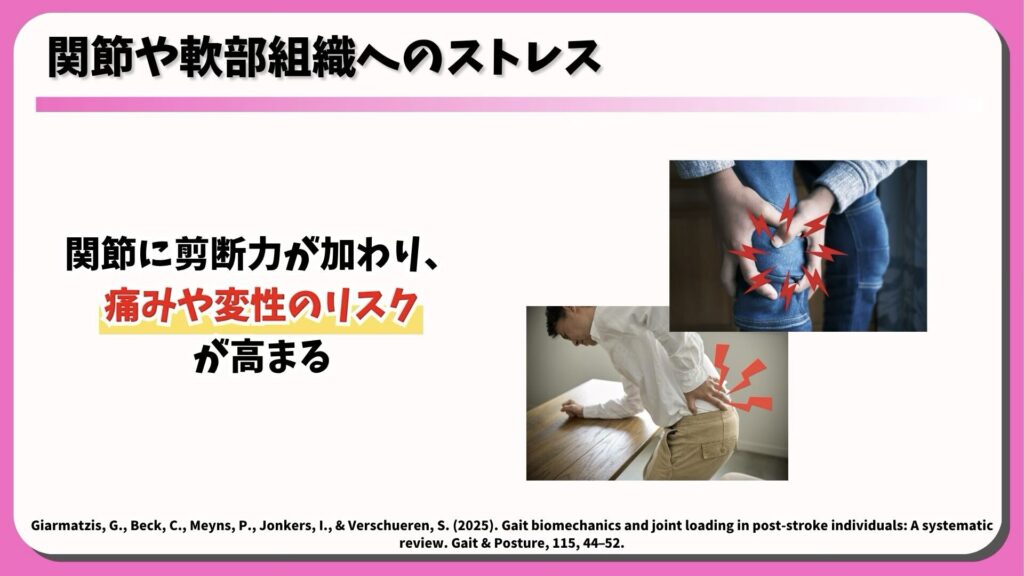
特に膝関節では、体を支えるための筋肉(伸展筋群)の反応が遅れると、地面からの衝撃をうまく吸収できません。その結果、膝関節への負担が大きくなり、長期的に膝の痛みに繋がることもあります(Pohlら, 2017)。
「痛いけど頑張って!」は禁物です。

2. スパスティシティ(筋緊張)の助長
麻痺側に努力的に「乗ろう」と意識しすぎると、かえって痙縮(スパスティシティ)が強く出てしまうことがあります。これは、急な感覚入力の変化が反射を刺激し、筋肉の過度な緊張を引き起こすためと考えられています(Nielsenら, 2018)。
リハビリ中に麻痺側の手足が突っ張ってしまうような経験はありませんか?それは、無理な荷重が原因かもしれません。筋緊張が高まると、さらに動きにくくなり、悪循環に陥ってしまいます。

3. 代償動作の固定化
麻痺側に無理やり体重を乗せようとすると、身体はバランスを取るために、骨盤を不自然にねじったり、体幹を傾けたりといった「見た目だけ左右対称」に見えるような動き(代償動作)を使ってしまいます。
このような非効率な動きを繰り返すと、脳がその誤ったパターンを学習し、それが「正しい動き」として固定化されてしまうリスクがあります(Hyndmanら, 2006)。結果的に、より自然で効率的な動きの習得を妨げてしまうことになります。
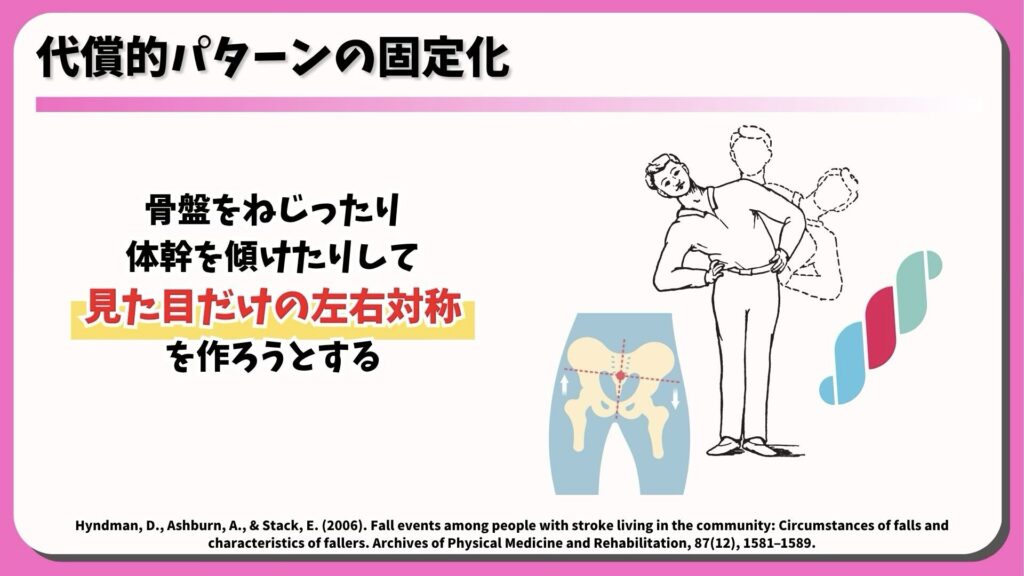
4. 筋疲労と疼痛の発生
脳卒中慢性期の患者様では、麻痺側の筋肉のエネルギー代謝能力が低下していることが知られています(Ryanら, 2011)。この状態で無理な荷重訓練を続けると、麻痺側の筋肉がすぐに疲労してしまい、痛みを生じる原因となります。
疲労した筋肉では、姿勢を保つ能力も低下し、かえってバランスを崩しやすくなることもあります。痛みや疲労感は、患者様の意欲低下にも繋がり、リハビリの継続を困難にさせます。
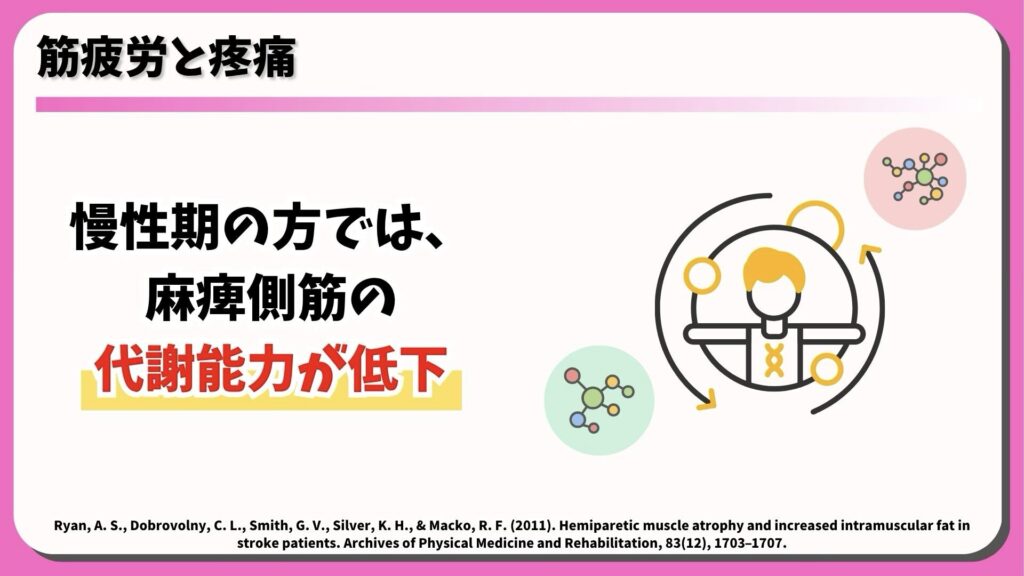
5. 非麻痺側への過剰な負担
麻痺側を頑張らせすぎると、身体は全体のバランスを取るために、健全なはずの非麻痺側に過剰な負担をかけてしまいます。
これにより、非麻痺側の筋肉も疲労し、関節に痛みが出たり、可動域が制限されたり、筋力が低下したりするといった問題が起こることも報告されています(Wareńczak-Pawlickaら, 2025)。
「良い方の足だから大丈夫」と思われがちですが、非麻痺側も酷使しすぎると、二次的な障害を引き起こすリスクがあるのです。

6. 誤学習(Maladaptive learning)
リハビリにおいて最も大切なのは、「うまくできた!」という成功体験の積み重ねです。
脳は成功体験を繰り返すことで、新しい運動パターンを学習し、神経のつながりを強化します(神経可塑性)(Kleim & Jones, 2008)。
しかし、不安定な状態で無理な荷重を繰り返すと、「この動きは危ない」「バランスが崩れる」といった誤ったパターンを脳が学習してしまいます。
これが「誤学習」です。一度誤学習が起こると、正しい動きを再学習するのに余計な時間と労力がかかってしまう可能性があります。

まとめ:「乗せる」より「支えられる」条件を整える
麻痺側荷重は、確かに機能回復に不可欠な要素です。しかし、今日お話ししたように、「ただ強く促すだけ」では、多くの弊害を生み出すリスクがあります。
大切なのは、「無理に体重を乗せること」ではなく、麻痺側が「自然に体重を支えられる」条件を丁寧に整えてから、重心がスムーズに移行するように促すことです。
- 関節の安定性:まずはアライメントを整え、関節が安定した状態で荷重できるかを確認する。
- 筋力の発揮:必要に応じて、荷重に耐えうる筋力を段階的に強化する。
- 感覚の入力:麻痺側からの感覚入力が適切に行われているかを確認し、必要であれば補助的な刺激も活用する。
- バランス能力:動的なバランス能力が向上することで、自然な重心移動が可能になる。
焦らず、患者様の身体が「準備できた」段階で、自然な重心移動を促すことが、最も効率的で安全なリハビリテーションへと繋がります。
最後に
「麻痺側荷重」は、ついつい「やらなきゃ」と患者様もセラピストも力が入ってしまうテーマかもしれません。
でも、心配しなくて大丈夫です。身体が準備できれば、重心は自然に戻っていきます。
今日の内容が、皆様の臨床において、麻痺側荷重への新たな視点やアプローチのヒントになれば幸いです。患者様一人ひとりの状態を丁寧に評価し、最適なバランスを見つけ出すことが、私たち専門職の腕の見せ所ですね。
それでは、また次回お会いしましょう!
📚 参考文献
- Giarmatzis, G., Beck, C., Meyns, P., Jonkers, I., & Verschueren, S. (2025). Gait biomechanics and joint loading in post-stroke individuals: A systematic review. Gait & Posture, 115, 44–52.
- Hyndman, D., Ashburn, A., & Stack, E. (2006). Fall events among people with stroke living in the community: Circumstances of falls and characteristics of fallers. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 87(12), 1581–1589.
- Kleim, J. A., & Jones, T. A. (2008). Principles of experience-dependent neural plasticity: Implications for rehabilitation after brain damage. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51(1), S225–S239.
- Nielsen, J. B., et al. (2018). Spasticity revisited: Disordered sensorimotor control following central nervous system lesions. Brain, 141(3), 728–743.
- Pohl, M., Mehrholz, J., Ritschel, C., & Rückriem, S. (2017). Speed-dependent treadmill training in ambulatory hemiparetic stroke patients: A randomized controlled trial. Stroke, 33(2), 553–558.
- Ryan, A. S., Dobrovolny, C. L., Smith, G. V., Silver, K. H., & Macko, R. F. (2011). Hemiparetic muscle atrophy and increased intramuscular fat in stroke patients. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 83(12), 1703–1707.
- Wareńczak-Pawlicka, M., et al. (2025). Functional asymmetry of lower limbs and compensatory changes in the non-paretic side after stroke. Sensors, 25(4), 1082.